アクセス数 529…606…625…633…665…683…715…723
7月6日 今日は貴農同志会の総会に出席しました。今日はホームカミングデーと言うことで、午後からは礼拝や記念講演などの行事が続きますが、連日の会議で少々疲れ気味のため午後は欠席することに決めました。今日は突然の理事長のあいさつがあり、何かが変わってきているのを感じました。

6月15日(土)突然の訪問者 朋遠方より来る。愛知から友人と一緒に自宅を訪問。これから定山渓に行くという。皆さん元気ですね。今日は酒を飲みすぎるかな。ゼミを超えたお付き合いが続くというのは理想ですね。学生時代の付き合いはどうだったのかな。でも、君たちの楽しんでいる姿を見るのは好きです。そのうち写真を送ってください。


お知らせ 2024年7月6日(土)
貴農同志会第31回総会9:30~10:30 酪農学園同窓生会館会議室
ホームカミングデー 記念植樹 11:15~(白樺並木) 記念礼拝13:00~
記念講演13:30~ 「アーバンベア~すみわけによる共存を目指して」(佐藤喜和教授)
「学園運営の報告」(岩野英知学長)
5月27日 石狩市に住んでいる卒業生のY君から電話が来た。と言ってもFBに投稿した返事と思う。奥様も石狩市で頑張っている様子。Y君は札幌市を中心に頑張っているようです。正道空手のほうも続いているようです。O君ともつながっているようですね。
4月1日 卒業生の岩本君からハガキが来た。37年間務めた製薬会社を定年退職したそうだ。定年後は好きな音楽、ギター演奏をして過ごしたいそうだ。続々定年を迎える卒業生がいますね。ご苦労様でした。60歳定年で、その後の生活設計はいいのかな。考えてみたら、その会社は転勤が多かったのではないかな。今の時代、定年後も65歳までは勤務できるみたいだけど、会社によっては違うのかな。ギターを弾いて過ごしたいそうなので、また違う人生を楽しみたいのでしょうね。近くに住んでいるようなので、機会があれば、また会いたいですね。
3月2日 僕と同期の同じゼミ仲間の逝去が掲載されていました。前触れもなく突然の知らせで、ビックリです。庭仕事中に突然心筋梗塞のようです。同じゼミ仲間もだんだんと人数が減っていきます。これはこれで寂しい現実ですね。100歳の方が言っていました。仲間がどんどんいなくなってしまうとのことでしたが、その気持ちよくわかります。
2月24日 網走の卒業生と電話でお話 突然ミカンを送ってきたので、ビックリ。何かあったのかと電話。今年の3月で任用期間も終わって、いよいよ定年を迎えるそうです。病気もあったりして、それでも無事定年を迎えて、おめでとうございます。彼は大学では7年在籍した猛者でしたね。偶然僕のゼミに入り、そのまま卒業していった方で、僕にバイクや木彫りを教えてくれた方でしたね。僕のバイクはまだ1台所有していますけど、そろそろおしまいの年になりそうです。また、木彫りはまだ僕は教室に通っていますので、もう少し続きそうです。自分のゼミ出身の方で退職時期を迎えたのは教員で一人、彼は二人目だと思います。ご苦労様でした。
2月15日 卒業生ともだんだん疎遠になってきました。考えてみたら当たり前の話です。僕自身前任者の桜井豊先生と卒業生と集まりましょうかということになって、集まってみたら5人しか集まらなくて、それ以降は先生を囲んで集まることは中止にしました。当たり前の話ですし、僕も今は地域のお年寄りの方々との集まりが中心です。卒業生たちもそれぞれ新しい社会が中心ですね。このホームページも今後どうするか考えなおさないといけないかな。80歳になる時が目安だな。あと8か月か。
2024年1月29日 足寄の卒業生と話 ある普及所の方の名前を使ってFBが来て、うっかり返事をしてしまって、なりすましだなと直感的に感じて卒業生に連絡。すでに彼は知っていたようです。本当に迷惑な話ですね。いったい何のために他人のFBを使ってそのようなことをするのでしょうか。僕も狙われないように注意しないと。
12月24日 卒業生の皆様、今年ももう少しで新年を迎えます。皆さんにとって今年は良い年でしたか。来年も穏やかな1年間になることを祈ります。メリー・クリスマス!&新年おめでとう!
12月23日 川島先生が来ていただいたのですが、ちょうど出かけていて、一瞬だけ車の後姿を見ただけでした。バターナッツかぼちゃですか?ありがとうございました。
12月13日 卒業生からポインセチアが。ありがたいことですね。

12月4日 夕張の卒業生と電話でお話。ずっと同じ職場で働いています。途中で辞められる方が多い中で継続されているのはすごいです。毎年1回はお話ししますが、いつも自宅まで来られることはありません。地元の方と結婚されてすっかり夕張の人になりました。今度こそ遊びに来てほしいものです。
11月7日 旭川から卒業生が寄ってくれました。new!
いつも忘れないで寄ってくれます。ありがたいことですね。彼が学生時代に大麻銀座商店街で「クラスタークラブ」というお店を皆で開いていましたが、白老から新鮮な魚を仕入れた時に、彼は魚をさばくことができました。また、実家が石狩ということもあって、石狩から魚を仕入れてさばいてくれていましたね。
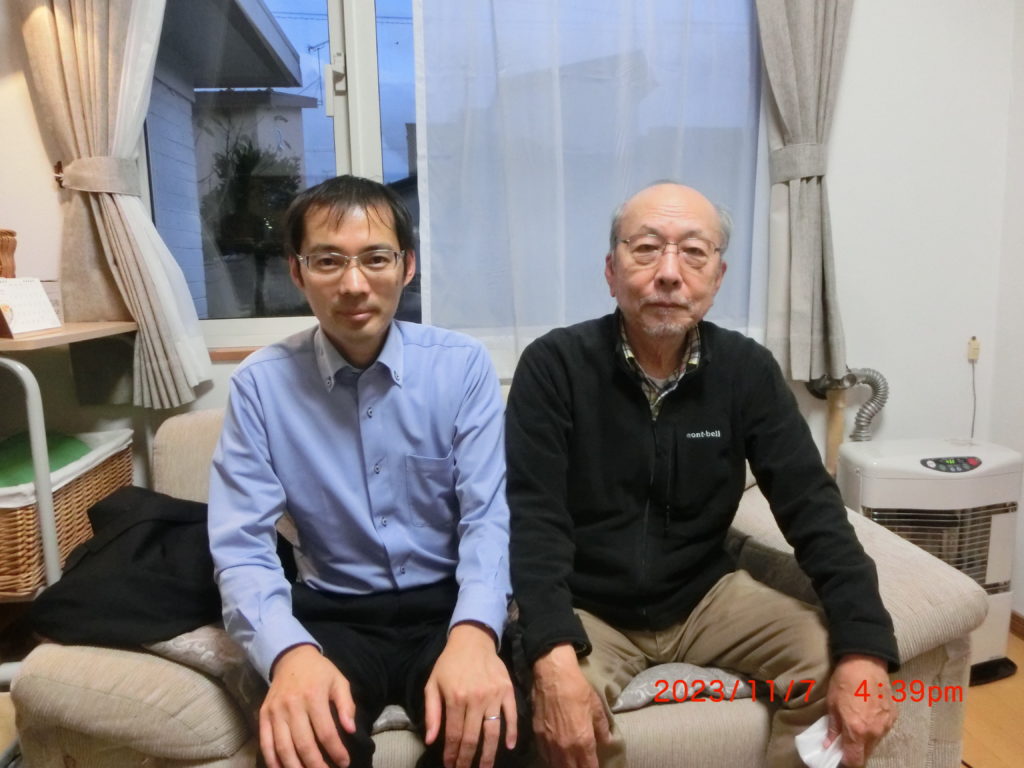
10月19日 富良野の卒業生と new!
いつもジャガイモと玉ねぎを送ってくれる卒業生とお話ししました。今年は暑さのために農作物にかなり被害が出たそうです。保険でも80%くらいまでしか補償はされないそうです。でも皆さん頑張っていますね。「農家を続けているという便り」だと言っていただけるのは感謝ですね。結婚して子供も生まれ、電話先でもその様子がわかります。
9月17・18日 番外編 最近「縄文式土器づくり」の時は、「江別縄文土器の会」の方々と一緒に指導に来られた方が酪農学園出身の方で、意外と近くに知り合いがいるみたいな感じで親近感を持てますね。機会があれば徐々に紹介したいと思います。


9月26日 40数年ぶりに再会果たす(同じ酪農学園大学の出身者です)
僕は笑顔が不得意なのですが、これでも笑顔のつもり。Yさん夫妻は笑顔が絶えないご夫妻で、一瞬にして長い間の空白期間が縮まります。

9月2日 岩見沢の友人からご家族の写真1枚(彼は同じ酪農学園大学の卒業生です)

8月5日 平成3年ゼミ卒業の皆さんと会う
お互いに姿かたちは少しづつ変わってきましたが、酒を酌みかわしていくと30年の隙間がなくなってくるから不思議ですね。昔の資料を用意してくれたり、お互いに地元の土産を交換し、近況を報告したりしていると時間はあっという間に経過して、お開きになりました。皆さんはその後札幌で2次会を開催したのでしょうが、飲みすぎは時として長い間の隙間を埋めるのに必要なことなのかもしれませんね。







9月7日 自宅前で。レガシーは廃車予定。軽トラ1台になります。

7月14日 貴農同志会の総会(酪農学園に勤務されていた方々の)


6月27日 北海道新聞 朝刊に
当ゼミ出身者の記事が載りました。かなり大きな記事でしたので、縮小しないといけません。後日掲載予定です。記事は「ディープに歩こう 第3部石狩・浜益④浜益和牛」となっています。

6月18日 卒業生(昭和62年)が自宅を訪問
58歳だそうですが、半袖とは若いですね。きしめんの会社(4店舗)を立ち上げているそうです。遠くから来て、昨日は仲間たちと会ってきたそうです。こうして忘れないで寄ってくれてありがとう。

6月17日いつものメンバーで 平成6年3月卒業

6月11日 同じ卒業生から
9月25日にお会いして、ご無沙汰していることもお詫びしないといけないですね。藤野の恩師のご自宅には訪問していたのですが、78歳になって近くの旧友に会いたくなって連絡してみました。お二人ともお元気なようで一安心です。お姿も変わらないですね。彼は大学を卒業後、北大で研究をされて公社にお勤めになっていました。僕はしがない大学院生でしたが、そこの公社でアルバイトの雑誌編集者でした。彼には良くしていただき感謝しています。

6月7日 同じ卒業生として(2)

5月23日 同じ卒業生同士として (同窓生会館にて) すっかりご無沙汰していました

平成6年3月卒業生の校長先生と電話(6)

2日前に電話して少しお話をしました。大阪で親友(同期の工藤ゼミ出身)と飲んでいる写真を拝見。2日後には東京で3人で飲んでいました。ラインでの交流も見ていましたので、お話をしたくなって電話。またお会いしましょう。(5.24)
卒業生から電話(5)平成3年3月卒業
つい2~3日前に卒業生から電話。先日普及員を定年退職した方と月形にたい肥をもらいに行ったことを知っていて、電話が来た。彼はJAに勤務をしていたが、縁があって普及員の試験に合格して現在は農業試験場に出向しているそうだ。彼の上司も僕のゼミ出身者であるので、仕事はしやすいに違いない。普及員の立ち位置は試験場の新技術を普及することにつながるので、重要な橋渡し役だ。いろいろ難しいことも多いと思うが、頑張ってほしい。普及員も自分で様々な技術や新種開発などの研究が多い。試験場の研究員たちと協力して、北海道の農業発展に努力してほしい。(5.21)
卒業生からの手紙(4)
農業改良普及センターに勤務をしている卒業生から転勤のあいさつが来ました。もともとは僕のゼミ出身者ではなかったけれど、縁があって大学院生として頑張った学生だった。普及員制度の下でその能力が十分に発揮できているのかどうか心配をしている。僕自身もう相当の期間普及機関との関係がないので現在はわからないけれど、それぞれの地域の中で、農家との密着型の農業指導がどの程度できるのか、個人の能力だけではどうしようもない環境の変化があるだろうね。頑張ってほしい。(5.15)
卒業生からの手紙(3)平成3年3月卒業
こちらは現役の先生からの手紙です。高校の校長としての転勤あいさつ文です。年度初めの転勤は入学生数が決まっていて、新任の先生と一緒に赴任するのであるから、それぞれかなり複雑な環境になるのかな。新しい職場に移って、今は新たな気持ちをもって毎日仕事に励んでいただいている時期ですね。いつまでも広い視野とチャレンジ精神をもって若い人たちを育ててください。(5.15)
卒業生からの手紙(2)昭和60年3月卒業
昭和60年にJAに入所して、定年を迎えたとのことで、その後は仕事の延長はせずにご両親の介助をされるそうです。ご家庭を優先されるのはいろいろな事情があるのでしょうね。ご苦労様です。私の場合は好きに生きているつもりで、いつの間にか家内に介護されている部分が多くなってきています。高齢化社会と言っても人それぞれの状況は異なっています。人生100年と言っていますが、そんなに簡単に割り切れる状況の方はそんなにいないことも確かです。安心できる社会にはとてもなっていませんね。(5.15)
卒業生からの手紙(1)昭和62年3月卒業 37年間道内の高校教員・校長先生を経て3月に定年退職したそうです。これを読むと定年退職とあります。60歳定年なんですね。その後の人生設計はわかりませんが、ご苦労様でした。教員という人生はどんなものだったのかはわかりませんが、山あり谷ありだったことでしょう。心の奥底にしまったままのものも多くあるだろうと思います。もう少し経つと、また新しい気持ちになるかな。(4.7)
2023年2月27日(月)浜益から卒業生が来てくれました。平成3年3月卒業 お米やジャガイモをたくさん持ってきてくれました。ありがとうございます。今年も図々しくたい肥をもらいに行こうかな。(2.27)

12月23日 年賀状は今後どうするかな。
今年も何とか年賀状を250枚くらい出したけど、戻ってくる枚数も多くて、今後どうするか迷いますね。だんだん管理ができなくなってきている背景もあります。メールでの年賀状もどうかと思うけど。
1月1日 賀正!
今日は朝からたくさんの卒業生を中心とする皆様からの年賀状もいただきました。新型コロナ感染拡大以来仲間が新型コロナに感染してしたりして、周りとの交流が少なくなってきています。皆さんは大丈夫でしょうか。我々老人同士の年賀状は「来年はもう年賀状はやめます」との文章がちらほら見られます。定年後12年経過しておりますので、卒業生の皆さんとも年賀状だけが便りとなってきました。年賀状そのものの管理も怪しいので、僕もそろそろおしまいかなとも感じだしてきましたが、ホームページはまだまだ頑張りますよ。僕の姿はだんだん小さくなって、怪しくなってきましたが、その姿を送り続けるのもいいかな。もうしばらく年賀状は続けるつもりです。80歳くらいまでが限界かな。(2023.1.1)
12月17日 同期の卒業生二人が訪ねて来てくれました。

11月23日 名寄から訪問してくれました。

9月14日 飲み会をしましたが、ちょっと体調が悪かった。影が薄いのはそのせいかな。

ホームカミングデー
酪農学園の校友会主催によるホームカミングデー(第29回)と白樺際(第26回)は7月2日に黒沢記念講堂にて開催されました。下村・工藤の2名がそれぞれ報告しました。何といっても同じゼミの出身者たちが集まってくれたことが一番うれしかったですね。(7.2)



写真を撮っていませんが

Facebook あまり興味を示せなくなって、自らはあまり投稿しませんが、トップの写真を変えたところ、急に「いいね」というのですか、その反応にびっくりしました。卒業生たちの反応も多く、それなりに見ることもあるのですね。あらためて、人のつながりを感じた次第。
2022年5月 卒業生が訪問 平成元年3月卒業

久しぶりに浜益に(4.25)
たい肥をもらいに家内と行ってきました。春なので忙しいみたいですね。申し訳なかったですね。お米や肉などたくさんいただきました。ありがとうございます。帰りには当別の友人にもたい肥とお肉のおすそ分けです。早速北広の畑や自宅の畑に撒いてます。



